はじめに
1986年の爆発的な隆盛を経て、1987年はその勢いを保ちながらも、メタルが枝分かれしていく過程が見えた年だった。商業的にはアメリカンハードロックが頂点を極め、スラッシュ勢は進化と洗練を遂げ、地下では新たな極限を探るエクストリームメタルが芽吹く。さらにヨーロッパでは、メロディックで物語性の強い音楽性が成熟期を迎えた。1987年は「メタル黄金期の絶頂」と同時に、「その先の未来への分岐点」でもあった。
アメリカンハードロック/LAメタルの絶頂(2年連続)
1987年は、商業的な成功とアリーナ規模のサウンドが最も眩しく輝いた年だった。派手なルックスと華やかなサウンドの陰で、各バンドはそれぞれの方向へと個性を研ぎ澄ませていく。GUNS N’ ROSESが放った『Appetite for Destruction』は、飾り気のないストリート感でLAメタルの本質を更新し、DEF LEPPARDの『Hysteria』は緻密なプロダクションとポップなメロディで、ハードロックを大衆音楽の頂点に押し上げた。WHITESNAKE『Whitesnake(1987)』は官能と叙情の融合、MOTLEY CRUE『Girls, Girls, Girls』は享楽と退廃の象徴、AEROSMITH『Permanent Vacation』は復活劇そのもの。この年、アメリカのハードロックは“最も華やかで、最も売れた”音楽として成熟の極みに達した。
GUNS N’ ROSES – Appetite for Destruction
1987年を象徴するアルバムといえば間違いなくこれ。LAの裏通りの暴力と欲望をそのままサウンドに閉じ込めたようなデビュー作だ。グラマラスな見た目に反して、アンダーグラウンドな怒りと焦燥がむき出しで、メタルとロックンロールの境界を溶かした。80年代後半の音楽シーンに、再び「危険なバンド」が登場した瞬間だった。
DEF LEPPARD – Hysteria
緻密さの極致。ドラマーのリック・アレンが事故で片腕を失うという悲劇を乗り越え、シンセを駆使して完成させた超大作。「Pour Some Sugar on Me」「Animal」など、どの曲も完璧に磨き上げられたポップメタルの結晶であり、80年代のメタルが大衆音楽として最高潮に達した象徴的アルバム。
WHITESNAKE – Whitesnake(1987)
デヴィッド・カヴァーデイルが全米制覇を目指して作り上げた究極のAORメタル。ジョン・サイクスによるギターが強烈にメロディアスで、「Still of the Night」や「Is This Love」は官能と哀愁が見事に融合。英国産ハードロックがアメリカ市場で頂点に立った記念碑的な一枚だ。
MOTLEY CRUE – Girls, Girls, Girls
享楽と退廃の極み。前作『Theatre of Pain』でポップ化した彼らが、再びダークでワイルドな路線に戻った。タイトル曲「Girls, Girls, Girls」はストリップクラブ賛歌でありながら、同時に当時のLAメタルシーンの空気そのものを封じ込めた記録でもある。サウンド的にはやや荒削りだが、それがまたこの時代の本質を表している。
AEROSMITH – Permanent Vacation
薬物依存で崩壊しかけたAEROSMITH が奇跡の復活を果たした一枚。ブルース・フェアバーンのプロデュースとデズモンド・チャイルドらのソングライター陣が加わり、80年代仕様のアリーナロックに進化。「Dude (Looks Like a Lady)」「Angel」など、70年代の泥臭さと80年代の華やかさが絶妙に融合した。彼らにとって“第二の黄金期”の幕開けとなった作品。
スラッシュメタルの進化
1986年の暴走を経て、1987年はスラッシュメタルが個性と技術を磨いた年となった。ANTHRAX『Among the Living』は社会風刺とユーモアを両立し、TESTAMENT『The Legacy』は正統派ヘヴィメタルの叙情をスラッシュに融合。CORONER『R.I.P.』はヨーロッパ勢ならではのテクニカル志向を打ち出し、DOOM『No More Pain』は東洋のアンダーグラウンドから世界水準のアグレッションを提示した。さらにD.R.I.『Crossover』は、ハードコアとスラッシュを融合させる新たな潮流を作り、後のクロスオーバー/メタルコアの礎を築いた。暴力と知性、アナーキーと構築性…。1987年は、スラッシュが“単なるスピード”を超えて芸術性へと歩み始めた節目だった。
ANTHRAX – Among the Living
スラッシュ四天王の中でも、最も陽性でストリート感覚を持っていたのがANTHRAXだ。本作は彼らの代表作であり、「Caught in a Mosh」「Indians」など、スピードとユーモア、そして社会性が見事に融合。スラッシュの激しさを保ちながら、パンクやヒップホップに通じるフレンドリーさを見せたことで、後のクロスオーバー文化にも大きな影響を与えた。
TESTAMENT – The Legacy
ベイエリアスラッシュの新星として鮮烈に登場したデビュー作。チャック・ビリーの咆哮とエリック・ピーターソンのリフ、そしてアレックス・スコルニックの流麗なギターソロが織りなす楽曲は、METALLICAやMEGADETHにも匹敵する完成度を誇る。伝統的ヘヴィメタルの構築美とスラッシュの攻撃性を融合させた、まさに“新世代スラッシュ”の幕開けを告げた傑作だ。
CORONER – R.I.P.
スイスから現れた技巧派スラッシャー、CORONERのデビュー作。彼らは単なる速さではなく、緻密な構成とクラシカルな旋律を重視し、知的でダークなスラッシュを展開。アルバム全体に漂う冷たい美学と、機械のような演奏精度は、後のテクニカルスラッシュの先駆けとなった。
DOOM – No More Pain
日本のスラッシュメタルにおける異端児、DOOMのデビュー作。単なるスラッシュではなく、変拍子やサイケデリックな展開を大胆に取り入れ、前衛的なセンスが際立つ。金属的な暴力性の中に浮遊感や狂気が共存し、のちの日本のオルタナティブ/プログレメタルにも通じる先鋭性を放っている。海外勢と比べてもまったく遜色のない異彩を放つ名盤だ。
D.R.I. – Crossover
ハードコアパンクから進化し、スラッシュとの融合を最初に実現した歴史的アルバム。そのタイトルがそのまま“クロスオーバースラッシュ”というジャンル名を生み出した。曲は短く、テンションは極限まで高い。パンクのスピリットとメタルの重量感が同居するこの作品は、1987年当時のアンダーグラウンドの爆発的なエネルギーをそのまま封じ込めている。
エクストリームメタルの胎動
メタルが「どこまで過激になれるか」という挑戦が始まったのもこの年だ。DEATH『Scream Bloody Gore』はデスメタルという新たなジャンルを産声とともに確立し、NAPALM DEATH『Scum』はハードコアとメタルの境界を粉砕して“グラインドコア”を生んだ。日本ではS.O.B.『Don’t Be Swindle』が同系統の激情を放ち、地下シーンから世界へ波紋を広げる。スウェーデンのBATHORY『Under the Sign of the Black Mark』は北欧ブラックメタルの礎を築き、CELTIC FROST『Into the Pandemonium』は芸術的実験精神でエクストリームの可能性を拡張した。1987年は、メタルが“破壊”だけでなく“創造”の極地に到達した年でもあった。
DEATH – Scream Bloody Gore
ここからすべてが始まった。チャック・シュルディナー率いるDEATHが放ったこのデビュー作は、デスメタルというジャンルそのものを定義づけた作品だ。ギターリフは重く、リズムは地を這い、ヴォーカルは人間離れしたグロウル。スラッシュの延長線上に新たな地獄を切り開き、以後のエクストリームミュージックの基準を塗り替えた。
NAPALM DEATH – Scum
この作品は、スピードと暴力性を極限まで突き詰めた“グラインドコア”の原典だ。政治的な怒りと無慈悲なサウンドが融合し、UKハードコアとメタルの境界を破壊した。もはや音楽というより衝撃そのもの、1987年のアンダーグラウンドに走った稲妻。
S.O.B. – Don’t Be Swindle
日本から世界に衝撃を与えたハードコア・スラッシュ。NAPALM DEATHとも親交が深く、のちにグラインドコア/デスメタルの世界的流れにも接続していく。生々しいノイズとテンションがほとばしるサウンドは、まさに“ジャパニーズ・エクストリーム”の原点であり、アンダーグラウンド精神の象徴ともいえる。
BATHORY – Under the Sign of the Black Mark
スウェーデンの孤高、クォーソンによるブラックメタル原典。粗削りながらも神話的なスケールと禍々しさが融合し、北欧の冷たい闇を音で描いた。ノルウェー勢が台頭する数年前に、すでにこの作品が存在したこと自体が奇跡であり、1987年のメタルが新たな“極北”へ踏み出した証でもある。
CELTIC FROST – Into the Pandemonium
スイスの異端、CELTIC FROSTが放った挑戦的な一枚。デス/スラッシュの枠を超え、インダストリアル、クラシック、ゴシック要素を大胆に導入。トム・G・ウォリアーの呻きと重厚なリフの間に、女性ヴォーカルやサンプリングが入り交じる実験性は、のちのブラック/ドゥーム/アヴァンギャルドにまで影響を与えた。混沌の中に新たな秩序を生んだ、真のカルトクラシックだ。
ヨーロッパメタルの成熟
北欧と中欧からは、メタルの新しい知性と叙情が台頭した。HELLOWEEN『Keeper of the Seven Keys, Part I』がメロディックスピードメタルの新世界を切り拓き、RUNNING WILD『Under Jolly Roger』は勇壮なパイレーツメタルを確立。WARLOCK『Triumph and Agony』ではドロ・ペッシュが女性ヴォーカルメタルの象徴となり、KING DIAMOND『Abigail』はホラーと劇性を融合した物語性で異彩を放つ。そしてPRETTY MAIDS『Future World』が叙情とキャッチーさの理想形を提示。ヨーロッパのメタルは、重さだけでなくメロディ、物語、構築美へと進化を遂げ、世界シーンの中で確固たる存在感を示した。
HELLOWEEN – Keeper of the Seven Keys, Part I
メロディックスピードメタルの始祖とも呼ばれる歴史的傑作。カイ・ハンセンからマイケル・キスクへとボーカルが交代し、より叙情的で壮大な世界観へと進化。「Future World」や「Halloween」に代表される勇壮なメロディは、後のパワーメタルシーン全体の基盤となった。
RUNNING WILD – Under Jolly Roger
海賊メタルという独自の世界観を打ち立てた作品。かつては悪魔主義的な歌詞が多かった彼らが、ここで一気に冒険ロマンへと舵を切った。タイトル曲の掛け声や疾走感は唯一無二で、後のパイレーツメタルムーブメントの原点となる。
WARLOCK – Triumph and Agony
ドロ・ペッシュ率いる女性ヴォーカル・メタルの最高峰。彼女のパワフルでエモーショナルな歌声が炸裂し、「All We Are」はアンセムとして世界中のメタルファンに愛され続けている。バンドとしては最後のアルバムだが、ドロ個人の伝説を決定づけた名盤だ。
PRETTY MAIDS – Future World
北欧メタルの洗練を象徴する一枚。ヘヴィメタルの鋭さとメロディアスなハードロックのキャッチーさを見事に融合させ、特にタイトル曲「Future World」はその象徴。バランス感覚に優れた“北欧メタルの理想形”といえる。
KING DIAMOND – Abigail
KING DIAMONDは既に1986年で紹介しているが、このアルバムを外すわけにはいかないので、1987年でも取り上げる。
ホラー映画のような構成と緻密な楽曲展開が光るコンセプトアルバム。亡霊屋敷を舞台にした物語を、演劇的なボーカルとギターの対話で描き出す。重厚でありながら美しく、メタルにストーリーテリングの可能性を提示した傑作だ。
最後に
1987年は、1986年の爆発的な成功をそのまま拡張・深化させた“黄金期の絶頂点”だった。ハードロックは商業的成功の極みを迎え、スラッシュは知性と技術を磨き、エクストリームメタルは新たな過激領域へ突入。そしてヨーロッパ勢は、美学と叙情を手に世界を席巻した。まだ「グランジ」も「オルタナ」も遠い未来の話。1987年は、メタルが最も多様で、最も強く、最も美しかった瞬間…。そのすべての枝が伸び切った、黄金時代の頂点にして“終焉への前奏曲”でもあった。
あくまでも1986年の流れの延長線上ということもあり、1987年は番外編という扱いにした。次回取り上げるのは1992年、グランジ旋風が吹き荒れてHR/HM黄金時代が終焉を迎えた年である。


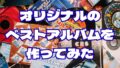

コメント