はじめに
1980年はHR/HM(ハードロック/ヘヴィメタル)において大きな転換点となった年である。イギリスからはNWOBHM(ニューウェイヴ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィメタル)の旗手たちが続々とデビューを果たし、シーンに新たなエネルギーを注ぎ込んだ。同時に、既に確立された大物バンドも次々と名盤を発表し、世代交代と共存のドラマが展開された。そしてその裏側では、1970年代を代表する巨人、LED ZEPPELINが解散を迎えるという象徴的な出来事もあった。新しい波と時代の終焉が交錯した1980年は、HR/HM史の中でも特別な位置を占める年である。そんな1980年のHR/HMを振り返ってみよう。
新世代バンドの台頭
70年代末のパンク/ニューウェーブの流行に押され気味だったハードロックだったが、80年に入るとイギリスから「NWOBHM(ニューウェイヴ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィメタル)」と呼ばれる新世代が次々に登場。より速く、攻撃的で若々しいメタルが生まれ、次代の主役が姿を現した。
IRON MAIDEN – Iron Maiden
IRON MAIDENのデビュー作『Iron Maiden』はNWOBHMの象徴的作品である。荒削りながらもスピードと叙情性を兼ね備え、スティーヴ・ハリスのベースを前面に押し出した独自のサウンドを確立している。タイトル曲「Iron Maiden」や「Prowler」など、ライブの定番として演奏される楽曲を収録し、後の黄金期を予感させる幕開けのアルバムである。
DEF LEPPARD – On Through the Night
DEF LEPPARDのデビュー作『On Through the Night』は、若さと勢いを全面に押し出した一枚である。キャッチーなメロディと硬質なリフは、彼らがアメリカ市場を意識していたことを示しており、「Rock Brigade」「Hello America」などの楽曲はその志向を端的に表している。後の大ヒット作に比べれば粗削りであるが、フレッシュなエネルギーこそが本作の魅力でと言えるだろう。
SAXON – Wheels of Steel
SAXONの2作目『Wheels of Steel』は、彼らをNWOBHMの中心的存在へと押し上げた作品である。重量感あるリフと直線的な力強さを備えた楽曲群は「747 (Strangers in the Night)」「Motorcycle Man」などライヴ定番曲を多数含み、観客を熱狂させた。ヘヴィでありながら耳に残るメロディを持ち、ブリティッシュ・メタルの王道を築き上げた重要作である。
DIAMOND HEAD – Lightning to the Nations
DIAMOND HEADのデビュー作『Lightning to the Nations』は、後のスラッシュメタル勢に絶大な影響を与えた伝説的アルバムである。「Am I Evil?」「The Prince」「Helpless」などはメタリカをはじめとする後進バンドにカバーされ、メタル史に名を刻む存在となった。複雑な展開と切れ味鋭いリフを兼ね備え、NWOBHMの枠を超えた革新性を示した作品である。
ANGEL WITCH – Angel Witch
ANGEL WITCHのデビュー作『Angel Witch』は、1980年のNWOBHMの中でも異彩を放つ作品である。オカルトや幻想的なテーマを扱った歌詞と、陰鬱さと叙情美を兼ね備えたメロディが独自の世界観を形成している。タイトル曲「Angel Witch」や「Atlantis」「White Witch」などは今なおカルト的な支持を集め、後のバンドへ影響を与えた。暗黒の美学を体現した一枚である。
中堅の躍進とベテランの復活
70年代からシーンを支えてきた大御所たちも、新しい形で蘇った。特にサバスとオジーは「袂を分かち、別々の成功」を収めた象徴的な年であり、AC/DCもボン・スコットの死を乗り越えて世界的な飛躍を遂げた。
JUDAS PRIEST – British Steel
『British Steel』はJUDAS PRIESTの代表作であり、ヘヴィメタルのスタンダードを確立した作品である。シンプルかつ鋭利なリフ、キャッチーで覚えやすいサビを備えた楽曲群は、メタルをより大衆的な音楽へと押し上げた。「Breaking the Law」「Living After Midnight」といった名曲は、今なおメタルアンセムとして歌い継がれている。
MOTORHEAD – Ace of Spades
『Ace of Spades』はMOTORHEADの代名詞的作品であり、荒々しい爆音と疾走感が詰め込まれた不朽の名盤である。特にタイトル曲「Ace of Spades」は、シンプルでありながら破壊力抜群のロックンロールとして、バンドの存在をロック史に刻みつけた。ヘヴィメタルとパンクの垣根を越えたサウンドは、その後のスラッシュメタルやハードコアにも直結する影響を与えている。
AC/DC – Back in Black
『Back in Black』は1980年にリリースされたAC/DCの大ヒット作であり、世界的に最も売れたロックアルバムの一つである。前任ボーカル、ボン・スコットの死を乗り越え、ブライアン・ジョンソンを迎えて制作された本作は、「Hells Bells」「You Shook Me All Night Long」「Back in Black」といった名曲を収録し、AC/DCのアイデンティティをさらに強固なものにした。ハードロックの王道を体現する究極の一枚である。
BLACK SABBATH – Heaven and Hell
『Heaven and Hell』はBLACK SABBATHがロニー・ジェイムズ・ディオを新たなボーカリストに迎えて制作した作品であり、バンドに新たな生命を吹き込んだ転換点である。トニー・アイオミの重厚なリフとディオのパワフルでドラマティックな歌声が融合し、表題曲「Heaven and Hell」をはじめ「Neon Knights」「Die Young」など、後期サバスを象徴する名曲が生まれた。ディオ時代の幕開けを告げる金字塔である。
OZZY OSBOURNE – Blizzard of Ozz
『Blizzard of Ozz』はオジー・オズボーンのソロデビュー作であり、ランディ・ローズの卓越したギタープレイによって不朽の名盤となった。哀愁漂うメロディとクラシカルな技巧が融合し、「Crazy Train」「Mr. Crowley」といった楽曲はメタル史に残る名曲として輝き続けている。BLACK SABBATH脱退後のオジーが自らの存在を証明し、ソロアーティストとして不動の地位を築いた作品である。
MICHAEL SCHENKER GROUP – The Michael Schenker Group
『The Michael Schenker Group』は元UFOのギタリスト、マイケル・シェンカーが自身のバンドで放ったデビュー作である。圧倒的なギターテクニックと美しい旋律が随所に散りばめられ、「Armed and Ready」「Victim of Illusion」などの名曲を生み出した。ハードロックとメタルを架橋するようなサウンドは、ギターヒーローとしてのシェンカーの評価を決定づけ、後のギタリストたちに多大な影響を与えた。
LED ZEPPELIN解散
1980年、HR/HMの新しい潮流が生まれる一方で、ひとつの時代が幕を閉じた。それがLED ZEPPELINの解散である。9月にドラマーのジョン・ボーナムが急逝し、バンドは「彼なくしてLED ZEPPELINは存在し得ない」として同年12月に正式な解散を発表した。1970年代を代表するロックアイコンであり、「ハードロックの原点」とも呼ばれる彼らの活動停止は世界中に衝撃を与えたが、その一方で後進のバンドたちはZEPPELINの遺産を受け継ぎながら、新しいサウンドを切り拓いていった。1980年はNWOBHMの台頭と同時に、ハードロックの「巨人」が去った年でもあり、まさに世代交代の象徴的な瞬間であった。
その頃、日本では
まだ「シーン」と呼べるほどの広がりはなく、80年代前半にLOUDNESSやVOWWOWが出てくる“土台”ができつつある段階と言えるだろう。
LAZY – 宇宙船地球号
『宇宙船地球号』はLAZYの5作目であり、アイドル的な路線から本格的なHR/HM志向へと大きく舵を切った作品である。高崎晃や樋口宗孝らの卓越した演奏技術が前面に押し出され、組曲的な構成やメッセージ性の強い楽曲群によってバンドの新たな姿を提示した。従来のファンを驚かせつつ、後のLOUDNESSや影山ヒロノブの活動へとつながる大きな転機となったアルバムであり、日本ロック史における意義深い一枚である。
※Spotifyになかった(TдT)
BOWWOW – TELEPHONE
『Telephone』は、BOWWOWが歌謡ポップ路線を追求していた時期に制作され、メジャーコード主体のポップな楽曲が特徴だ。バンドは次作『HARD DOG』でハードロックに回帰、これが後のVOWWOWにつながる。
最後に
1980年という年は、HR/HMが単なる流行ではなく、確固たる音楽ジャンルとして世界的に定着していく転換期であったと言えるだろう。新鋭の登場はジャンルの可能性を拡大し、ベテラン勢の名盤はその基盤を強固にし、そして巨人の終焉は新たな時代への道を開いた。
Part2では、第2の転換期と言える1986年を取り上げたい。



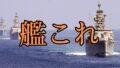
コメント