はじめに
1992年。ハードロック/ヘヴィメタルという巨大なジャンルが、ひとつの時代を終えて次の時代へと形を変え始めた年だった。80年代に世界を席巻したグラマラスなサウンドや技巧派ギタリストの時代は幕を閉じ、かわって台頭したのは“グランジ”という、飾り気のないリアルなロック。NIRVANAの『Nevermind』が全米1位を獲得したとき、若者たちの心はすでにメタルから離れつつあった。
だが、メタルは終わらなかった。アーティストたちは現状に抗い、新たな表現を模索しはじめる。スラッシュは重量感とグルーヴを増し、メロディック勢は深化と叙情を追求し、そしてプログレッシブやゴシックといった新しい枝葉が芽吹いていった。
まさにこの年は、HR/HMが「生き残るために変わる」ことを決意した瞬間だった。華やかな黄金期が終わりを告げる中、世界中のバンドたちがそれぞれのやり方で、次の時代への橋を架けようとしていたのである。
吹き荒れるグランジ旋風
1992年のロックシーンは、ハードロック/ヘヴィメタルの黄金時代が終わりを迎え、グランジという新たな潮流が主役へと躍り出た年だった。派手なルックスと技巧主義で支えられた80年代的メタルとは対照的に、グランジは倦怠と怒り、そしてリアルな生々しさをむき出しにした。その象徴が、シアトルを中心に台頭したNIRVANA、SOUNDGARDEN、PEARL JAM、ALICE IN CHAINS、そして少し遅れて登場したSTONE TEMPLE PILOTSらの存在である。彼らはメタル的な重量感を保ちながらも、虚飾を排したサウンドと内省的な詞世界で、若者たちの心を掴んだ。1992年は、まさにグランジが主流ロックを制圧し、既存のHR/HMがその地位を失っていった転換点だった。
NIRVANA – Nevermind(1991年)
前年末にリリースされた本作は1992年に爆発的に広まり、グランジを世界的ムーブメントへと押し上げた。カート・コバーンの不安と怒りを孕んだメロディ、そして「Smells Like Teen Spirit」に象徴されるキャッチーさと破壊衝動の同居は、若者たちの鬱屈を代弁した。メタルの技巧とは無縁のラフな演奏、しかし強烈なフックと感情のリアルさによって、「かっこつけないロック」が新たな美学となった。
SOUNDGARDEN – Badmotorfinger(1991年)
グランジ勢の中でも、特にヘヴィメタルの影響を強く残していたのがSOUNDGARDENだった。クリス・コーネルの圧倒的な歌唱力と、トニー・アイオミ直系の重くねじれたリフが共存し、サバス的暗黒感とプログレッシブな構築美を融合している。シーンの中で最も「メタル寄り」な存在として、グランジとHR/HMの橋渡し役を果たした重要作だ。
PEARL JAM – Ten(1991年)
よりクラシカルなロックの系譜を感じさせるのがPEARL JAMのデビュー作『Ten』である。エディ・ヴェダーの魂のこもった歌声と、アリーナロック的なメロディセンスが融合し、グランジ勢の中でも最も普遍的な感動をもたらした。ブルースやハードロックの伝統を下地にしながらも、90年代的な誠実さと社会への視点を織り込んだ作品として、後のオルタナティブロックの定義を広げた。
ALICE IN CHAINS – Dirt
グランジの中でも最もダークで、ヘヴィメタル的な側面を強く持つのがこの『Dirt』だ。ドラッグと絶望に沈む世界をレイン・ステイリーが重苦しく歌い上げ、ジェリー・カントレルのリフは鈍くうねる。サウンド的にはメタルに極めて近いが、内省と破滅のリアリズムが決定的に異なる。グランジが単なるファッションではなく、精神的深淵を描く表現であることを示した傑作である。
STONE TEMPLE PILOTS – Core
やや後発のグランジ勢として登場したSTONE TEMPLE PILOTSは、NIRVANAらの直系と見なされつつも、よりハードロック的な構成美とグルーヴ感を持ち込んだ。『Core』はその重厚なサウンドとキャッチーなメロディで商業的にも成功し、グランジのスタイルを大衆的に定着させた作品といえる。スコット・ウェイランドの多面性のあるヴォーカルも、90年代ロックの多様化を象徴していた。
再構築を迫られたアメリカンハードロック/アリーナロック
グランジ旋風が吹き荒れる中、80年代を象徴したアメリカンハードロック/アリーナロック勢は、派手なルックスと享楽的なテーマを捨てざるを得なかった。バブル的な華やかさは時代遅れと見なされ、真摯さや内省を求めるリスナーの空気が主流になっていたのである。そんな中で、MR. BIGやBON JOVI、DEF LEPPARDらはそれぞれのやり方でサウンドの再構築を試みた。技巧やスケール感を維持しながらも、より人間的で、現実と向き合うロックへの模索が始まったのがこの時期だった。
MR. BIG – Lean into It(1991年)
グランジ前夜に発表された本作は、アメリカンハードロックの完成形とも言える。技巧派の集合体ながら、派手なインストではなく「To Be with You」に代表されるシンプルで温かみのあるメロディで世界的成功を収めた。ハードロックの枠を超えた普遍的ポップセンスは、過剰な装飾を排除する90年代的感性にも通じ、グランジ時代にも生き残れるバンド像を提示した。彼らは「テクニックを持つが、それを誇示しない」スタイルで、時代の変化に最も柔軟に適応したグループの一つだった。
BON JOVI – Keep the Faith
80年代のアリーナロックを象徴したBON JOVIも、ここで大胆な変化を見せた。長髪とスパンコールを脱ぎ捨て、より現実的で内省的なテーマを扱い、サウンドもグルーヴ感とブルース要素を増した。「Bed of Roses」などに見られる成熟した叙情性は、時代の要請に応えた“大人のロック”として高く評価された。グランジ時代を生き延びるための再出発点といえる作品である。
DEF LEPPARD – Adrenalize
スティーヴ・クラークの死という悲劇を経て完成した本作は、80年代的な大仰さを残しつつも、メンバーの絆と再生の物語として響いた。『Hysteria』の延長線上にありながら、より内省的で抑制の効いたメロディが特徴で、グランジ的な“素の感情”に少し歩み寄った印象もある。時代の変化に抗うように完成度を追求した本作は、アリーナロック最後の輝きともいえる。
W.A.S.P. – The Crimson Idol
過激なショックロックで知られたW.A.S.P.が、ここでまさかのコンセプトアルバムを打ち出した。ロックスターの虚栄と孤独を描くストーリー仕立ての本作は、ブラッキー・ローレスの自己投影的な内面告白でもあり、グランジ以降の“等身大の痛み”をメタル的文脈で表現した点が重要だ。サウンド面でも劇的な展開とメロディの繊細さが共存し、80年代的な様式美を保ちながらも精神性を深化させた。
EXTREME – III Sides to Every Story
『Pornograffitti』で華やかな成功を収めたEXTREMEが、その次に出したのがこの野心作だ。アルバムは「Yours」「Mine」「The Truth」という三部構成で、人間の内面と世界への視点をテーマにしている。ハードロックの枠を超え、クラシックやプログレ的要素まで取り込んだ本作は、90年代的な「知的で誠実なロック」への回答だった。グランジ的シニシズムに対して、理想主義的ロックの可能性を示した稀有な作品である。
変化を進めるスラッシュメタル勢
90年代初頭、スラッシュメタルはその頂点を過ぎ、変革を迫られていた。80年代後半に築いた攻撃性とスピードの美学は飽和し、リスナーの関心はより重く、深く、感情的な音へと移行していた。METALLICAの成功がその象徴であり、他のバンドたちもサウンドを引き締め、曲構成を洗練させる方向へと舵を切る。グランジやオルタナが新時代のロックとして台頭する中で、スラッシュ勢は“自らを再定義する”ことで生き残りを図ったのである。
METALLICA – Metallica(1991年)
通称“ブラックアルバム”。それまでの複雑で荒々しいスラッシュ路線から一転、ミドルテンポ主体の重厚で引き締まったサウンドに移行した。プロデューサーのボブ・ロックによる徹底した音作りと、ジェイムズ・ヘットフィールドのソングライティングが結実し、「Enter Sandman」「The Unforgiven」などが世界的ヒットに。スラッシュの先鋒が“メタルそのものの王道”へと進化したことで、ジャンルの境界を越えた普遍性を手に入れた歴史的転換点だった。
ANTHRAX – Attack of the Killer B’s(1991年)
こちらは新作というより、当時のバンドの方向性を示すブリッジ的コンピレーション。カバー曲やB面集の体裁ながら、PUBLIC ENEMYとのコラボ「Bring the Noise」が話題をさらい、スラッシュとヒップホップの融合を大胆に提示した。80年代的なメタルの形式を超え、ユーモアとストリート感を取り入れるANTHRAXらしい自由さが光る。後の“オルタナティヴメタル”潮流への伏線とも言える重要な一歩だった。
MEGADETH – Countdown to Extinction
デイヴ・ムステイン率いるMEGADETHも、ここでサウンドの方向転換を図った。スピードと複雑さを抑え、より洗練された構成とメロディを導入し、「Symphony of Destruction」「Sweating Bullets」などのヒットを生んだ。社会的・政治的メッセージを維持しながらも、重厚なグルーヴと明快な楽曲構成で、メタルのメインストリームに肉薄。METALLICAに続く“成熟の形”を示した作品である。
TESTAMENT – The Ritual
ベイエリアスラッシュ勢の中で最もドラマティックな変化を遂げたのがTESTAMENTだった。本作ではスピードを抑え、メロディを重視したトラディショナルなメタルへと接近。チャック・ビリーのボーカルもより叙情的で、ギターのトーンも落ち着いた印象に仕上がっている。スラッシュからヘヴィメタルへの橋渡し的作品であり、90年代以降の彼らの方向性を決定づけた。
EXODUS – Force of Habit
スラッシュ創成期からの古参であるEXODUSも、時代の流れに合わせて音楽性を変化させた。本作ではスピードよりもグルーヴを重視し、ブルースやハードロック的要素を導入している。攻撃性よりも重量感を追求した結果、従来のファンから賛否を呼んだが、スラッシュが新たな表現領域を模索していた当時の空気をよく表している。もはや「速いだけでは生き残れない」という現実を象徴する一枚だった。
ノリに乗るグルーヴメタル
スラッシュメタルが過渡期を迎えた90年代初頭、その空白を埋めるように登場したのが「グルーヴメタル」だった。テンポを落とし、リフの“重さ”と“ノリ”を前面に押し出したこのスタイルは、メタル本来のフィジカルな快感を再発見し、同時にグランジやオルタナが持つリアルな質感にも通じていた。過剰な技巧やスピードから距離を置き、怒りや攻撃性をよりプリミティブに表現したこの潮流は、1992年という混沌の時代において、メタルの新しい生存戦略となった。
PANTERA – Vulgar Display of Power
「グルーヴメタル」という言葉を決定づけた金字塔。フィル・アンセルモの怒号とダイムバッグ・ダレルの鋭利なリフが織りなす暴力的グルーヴは、当時のメタルに新たな基準を打ち立てた。速さではなく「重さ」で圧倒するスタイルは、スラッシュの進化形としても、グランジ以降の時代感覚としても完全に時代の核心を突いていた。「Walk」「Mouth for War」など、シンプルながら巨大なうねりを生むリフの力は、90年代メタルの代名詞となった。
EXHORDER – The Law
PANTERAと同時期に似た方向性を打ち出していたのが、ルイジアナのEXHORDER。彼らの2作目『The Law』は、PANTERAが確立する以前から“グルーヴスラッシュ”を提示していたと評価される作品だ。泥臭く、南部的なブルースの匂いを帯びたリフと、喉を裂くようなヴォーカルが特徴で、後続のグルーヴメタル勢に決定的な影響を与えた。今では“PANTERAの原型”と称されることも多い、知る人ぞ知る先駆作である。
HELMET – Meantime
ニューヨークの地下シーンから登場したHELMETは、グルーヴメタルを知的に再構築した存在だった。ポリリズム的なリフ、無機質でタイトなサウンド、そして感情を抑制したヴォーカル。それらはメタルとオルタナの架け橋となり、後の“ポストメタル”や“ニューメタル”へと影響を及ぼした。『Meantime』はその代表作であり、数学的精度を持つリフの反復が生む独特の緊張感は、スラッシュの暴力とは異なる都市的ヘヴィネスを提示している。
WHITE ZOMBIE – La Sexorcisto: Devil Music Volume One
ホラーとB級映画的感性をミクスチャーした異形のグルーヴメタル。ロブ・ゾンビ率いるWHITE ZOMBIEは、サンプラーやファンク的ビートを大胆に導入し、“踊れるヘヴィメタル”という新境地を切り開いた。『La Sexorcisto』はそのブレイク作で、「Thunder Kiss ’65」などのキャッチーでサイケなリフがMTVでも人気を博した。金属的な重量とカルト的ポップセンスを融合させた本作は、90年代メタルの多様化を象徴する存在である。
混沌の中のデスメタル
1992年、メインストリームではグランジが覇権を握り、スラッシュ勢が変化を模索する中、アンダーグラウンドではさらに過激で残酷な音楽が胎動していた。80年代後期に誕生したデスメタルは、ここにきて世界各地で独自の進化を見せる。フロリダを中心とするアメリカ勢はテクニカル化と残虐性の追求に向かい、ヨーロッパでは叙情や構築美を持ち込むバンドが現れた。技巧・音圧・精神性…。あらゆる要素が限界まで押し広げられたこの時期、デスメタルは“音の混沌”そのものとなっていった。
CANNIBAL CORPSE – Tomb of the Mutilated
アメリカンデスメタルの象徴にして、グロテスクの頂点。ジャケットと歌詞の残虐性で問題視されながらも、音楽的には驚くほど緻密なリフとグルーヴを持つ作品だ。「Hammer Smashed Face」に代表されるように、クリス・バーンズの咆哮とアレックス・ウェブスターのベースが生み出す圧倒的な低音は、デスメタルの教科書と化した。倫理的タブーを突破し、ジャンルの限界を拡張した決定的名盤。
OBITUARY – The End Complete
フロリダデスメタルの重鎮OBITUARYによる3作目は、彼らのスタイルを完成させた作品である。テンポを極端に落とし、リフの「鈍重なうねり」で圧倒するそのサウンドは、スラッシュの残滓を完全に脱ぎ捨てた。ジョン・ターディの“言語化不能な”呻き声のようなヴォーカルも独自で、ブルータルさよりも”腐臭を帯びたグルーヴ”が特徴的。デスメタルを“遅く、重く、暗く”深化させた作品として後進に多大な影響を与えた。
DEICIDE – Legion
反キリスト主義を前面に掲げるデスメタルの異端者DEICIDEが、デビュー作をさらに狂信的に進化させたのが本作。ブラスティングの嵐、悪魔的ハーモニーを駆使したヴォーカル、複雑なリフ構成と、すべてが過激化している。スピリチュアルな不快感とテクニカルな演奏が一体化した異様な緊張感を放ち、まさに“宗教的狂気”を音にしたようなアルバム。90年代初頭のアメリカンデスメタルの尖端を示す代表作である。
VADER – The Ultimate Incantation
ポーランド出身のVADERが放ったデビュー作は、東欧メタルの新章を開く衝撃作だった。スラッシュ由来のスピードと、デスメタルの低音リフを融合させたサウンドは、同時期のアメリカ勢にも引けを取らない完成度を誇る。荒削りながらも正確無比なドラムと鋭いギターが生む緊張感は、冷戦後の東欧から現れた“新たな暴力性”として注目された。地域性を超え、世界的デスメタルの一翼を担う起点となった作品。
AT THE GATES – The Red in the Sky Is Ours
スウェーデンのAT THE GATESによるデビュー作は、後の“メロディックデスメタル”誕生の原点に位置する。ヴァイオリンの導入や叙情的なリフなど、当時のデスメタルでは異例の要素を多数取り入れ、混沌と叙情がせめぎ合う音像を作り出した。トーマス・リンドバーグの絶叫は激情そのもので、暴力と哀しみを同居させる独特の美学を確立。デスメタルの中に“北欧の叙情”という新たな次元を切り開いた歴史的1枚である。
闇から生まれたブラックメタル
1992年、デスメタルが肉体の破壊を極める中、北欧では精神の暗黒を描く新たなムーブメントが台頭していた。それが「セカンド・ウェーブ・オブ・ブラックメタル」である。彼らは悪魔崇拝や反キリスト教、自然崇拝といった思想を掲げながら、音楽的には荒涼としたローファイサウンドと冷たいメロディを特徴とした。技巧や整合性を拒絶し、宗教的とも言える“闇の純度”を追求したこの潮流は、金属音楽を芸術や信仰の領域へと押し上げた。1992年は、その黒い炎が世界に広がり始めた原点の年である。
DARKTHRONE – A Blaze in the Northern Sky
ノルウェーブラックメタルを象徴する金字塔。もともとデスメタルを演奏していた彼らが、意図的に音質を劣化させ、寒気を感じさせるリフとノイジーなトレモロを前面に押し出したことで、ブラックメタルの美学を確立した。冷たく乾いたギター、霜のように白い空間、そしてフェンリズのプリミティブなドラムが作り出す「北欧の闇」は、このジャンルの教典となった。荒削りながらも、信仰に近い純粋さを放つ作品。
BURZUM – Burzum
唯一無二の存在、ヴァルグ・ヴィーケネスによるソロプロジェクトのデビュー作。デスメタル的な激しさではなく、内省と孤独を極端に押し出したサウンドが特徴で、反復するリフと簡素な構成から、宗教儀式のような没入感を生み出す。「黒の精神世界」への没入という点で、ブラックメタルを単なる音楽から”哲学的体験”へと昇華させた転換点でもある。以後のアンビエント寄り展開を予感させる静謐さも宿している。
IMMORTAL – Diabolical Fullmoon Mysticism
DARKTHRONEやMAYHEMと並ぶノルウェー勢の中で、最もファンタジックかつ神話的な世界観を提示したのがIMMORTALだ。本作はデビュー作にして彼らの基盤を確立した作品であり、氷の王国“Blashyrkh”を舞台とする独自の物語性がすでに現れている。ノルウェーの極寒を思わせる冷たいトーンと、疾走感の中に漂う叙情が融合し、後の“エピックブラックメタル”の原型となった。
MARDUK – Dark Endless
スウェーデン発のMARDUKによるデビュー作は、ノルウェー勢よりもデスメタルに近い音作りながら、闇への執着という点で共通している。スピードと重厚さを兼ね備え、後に見せる“超高速ブラスト”スタイルの萌芽がここにある。冷たさよりも血と硫黄の臭いを感じさせる本作は、北欧ブラックメタルが単一の美学ではなく、国ごとに異なる暗黒の形を持っていたことを示している。混沌から秩序へ向かう過程の記録とも言える作品だ。
独自の道を歩むヨーロッパ勢
アメリカでグランジ旋風が吹き荒れる中、ヨーロッパのHR/HM勢は別の方向へ進化していた。80年代の商業主義を引きずるのではなく、クラシック音楽や神話的世界観、そして郷愁に満ちたメロディを武器に「芸術としてのメタル」を追求していったのである。国ごとに個性が際立ち、北欧の叙情、ドイツの荘厳、スカンジナビアの旋律美が融合し、後のメロディックメタル/パワーメタル黄金期へとつながっていった。1992年はその分水嶺にあたる年だった。
YNGWIE MALMSTEEN – Fire and Ice
ネオクラシカルメタルの帝王が、円熟と暴走の狭間で放ったアルバム。圧倒的なテクニックとバロック的旋律は健在ながら、同時にキャッチーなメロディや歌心も重視されており、インギー流ポップ感覚の到達点とも言える。「Perpetual」や「Cry No More」ではクラシックの構築美を、「Teaser」では軽快なロックフィールを見せ、技巧一辺倒ではない幅の広さを示した。90年代においても彼が“様式美”の象徴であり続けたことを証明する一作。
PRETTY MAIDS – Sin-Decade
デンマークの叙情派が復活を遂げたアルバム。前作での商業的迷走を経て、本作ではメロディックメタル本来のダイナミズムを取り戻した。硬質なリフと哀愁漂うメロディのバランスが絶妙で、「Please Don’t Leave Me」の感涙バラードは彼らの代名詞となった。北欧らしい透明感と80年代的なエネルギーが共存する、移行期ヨーロピアンメタルの理想的な形を示している。
BLIND GUARDIAN – Somewhere Far Beyond
ドイツが誇るファンタジーメタルの金字塔。スピードメタルからプログレッシブな叙事詩へと進化した彼らの重要作であり、文学的世界観と壮大なコーラスワークが融合している。「The Bard’s Song」シリーズは以後のライブでも定番となり、メタルを“語り部の音楽”として再定義した。壮麗なメロディ、緻密なアレンジ、そして想像力の飛翔。メタルがまだ夢を語れることを証明した作品。
STRATOVARIUS – Twilight Time
フィンランドから登場した新星が、後のメロスピ時代を予感させる力作。クラシカルなギターとシンセサイザーの調和、そして透明感のある旋律がすでに確立しており、後の『Episode』や『Visions』への布石となる作品である。疾走感よりも叙情性が前面に出ており、北欧メタルらしい繊細な美意識を感じさせる。「Break the Ice」などには、寒冷な空気と人間的情熱の融合が見事に現れている。
FAIR WARNING – Fair Warning
元Zenoのメンバーを中心とした職人バンドによるデビュー作で、極上のメロディとハーモニーが詰め込まれている。「Longing for Love」や「One Step Closer」に聴ける繊細な哀愁は90年代ハードロックの理想形。時代に逆行しながらも、信念を貫いた一枚だ。
新たに生まれた潮流
1992年は、ハードロックやスラッシュメタルが構造的に揺らぐ中で、新しいメタルの可能性が一斉に芽吹いた年だった。技巧と知性を融合したプログレッシブメタル、鬱屈と荘厳さを併せ持つドゥームゴシック、皮肉と絶望を武器にしたオルタナゴシック、そして社会的怒りをサウンドに変えたラップメタル。いずれも既存のカテゴリーに収まらず、90年代以降のヘヴィミュージックの多様化を決定づける礎となった。
DREAM THEATER – Images and Words
技巧派メタルの代表格として、90年代のメタル界に新たな方向性を示した名盤。信じがたい演奏力を誇るメンバーたちが、複雑な構成と叙情的メロディを両立させ、メタルにプログレッシブロックの構築美を取り入れた。「Pull Me Under」はシングルヒットを記録し、インテリジェンスと熱量を兼ね備えたメタルとして世界的成功を収める。速さや攻撃性よりも“知的興奮”を提示したこの作品は、ポストスラッシュ時代の新たな旗印となった。
PARADISE LOST – Shades of God
デス/ドゥームの中核から、ゴシックメタルへと進化を始めた重要作。重く沈むギターリフと、ニック・ホルムズの低く呻くようなヴォーカルが織りなす世界は、絶望と美しさが同居する。前作までのデスメタル的要素を残しつつも、よりメロディアスで宗教画のような荘厳さを獲得し、次作『Icon』『Draconian Times』へ続く変貌の序章となった。暗黒の中にロマンを見出した“耽美系メタル”の始まり。
TYPE O NEGATIVE – The Origin of the Feces
ブルックリン発、皮肉と退廃のゴシックメタル集団による問題作。ライブ盤風のスタジオ盤であり、観客のヤジやノイズを挿入することで、虚構と現実をねじ曲げるような演出が施されている。ピーター・スティールの低音ヴォーカルとスローテンポのリフは、鬱屈とユーモアを共存させ、後の“オルタナゴシック”路線を決定づけた。退廃美とシニカルさが混ざり合う、唯一無二の存在感。
RAGE AGAINST THE MACHINE – Rage Against the Machine
メタルの重量感とヒップホップのリズムを融合し、社会への怒りを爆発させた革新作。「Killing in the Name」に代表される攻撃的リフと政治的メッセージは、オルタナティヴ/ニューメタルの原点となった。トム・モレロのギターはもはやエフェクトの実験装置と化し、ザック・デ・ラ・ロッチャのラップは徹底的にシステムへの抵抗を訴える。90年代以降のロックが“闘争の音楽”へ回帰するきっかけを作った歴史的作品だ。
岐路に立たされたベテラン勢
1992年、ヘヴィメタルの創始者たちにとって、それは試練と再定義の年だった。グランジが若者の怒りを代弁し、メタルの様式美が“時代遅れ”と見なされる中で、長くシーンを支えてきたレジェンドたちは、自らの存在意義を問い直さざるを得なかった。過去の栄光をなぞるのではなく、“今”の音でメタルを鳴らすこと…。その苦闘と決意が、1992年のベテラン勢には刻まれている。
BLACK SABBATH – Dehumanizer
オジー・オズボーンではなく、ロニー・ジェイムス・ディオを再び迎えて制作された重厚な作品。80年代後半のトニー・マーティン期を経て、ここで彼らは原点回帰を果たす。ドゥーム的重厚感と、社会へのシニカルな視線を融合させたサウンドは、90年代のヘヴィミュージックにも通じる硬質さを備えていた。「Computer God」「TV Crimes」などに見られる冷徹な機械文明批判は、まさに時代に抗う老練の知性。往年の神秘性よりも、現実への怒りを選んだサバスの“黒い再生”だ。
IRON MAIDEN – Fear of the Dark
ブレイズ・ベイリー加入前、ブルース・ディッキンソン最後のアルバムとして知られる。音楽的には迷いの時期でありながら、「Afraid to Shoot Strangers」やタイトル曲「Fear of the Dark」など、ライブ定番となる名曲を生み出した。複雑な時代にあっても、メイデンらしい叙事詩的メタルの魂はまだ息づいており、勇壮さと哀愁が交錯する。だが同時に、メンバーの内側では方向性の齟齬が生まれており、ひとつの時代の終わりを感じさせる作品でもある。
JUDAS PRIESTからロブ・ハルフォードが脱退
アルバムとしては1990年の『Painkiller』で頂点を極めた彼らだが、ツアー終了後にフロントマンのロブ・ハルフォードがバンドを離脱。1992年に正式発表され、黄金期の終焉が現実となった。時代の変化に抗いながらも、メタルという形式そのものを拡張しようとした彼の姿勢は、のちにFIGHTやHALFORD名義で結実することになる。グランジやオルタナが主流化する中、メタルの精神を次の形に引き継ぐ者としての役割を模索した彼の決断は象徴的だった。
その頃、日本では
世界がグランジと新潮流に揺れる1992年、日本のハードロック/ヘヴィメタルシーンは独自の成熟と分化を見せていた。80年代後半に培われたテクニックとメロディ志向を土台に、バンドたちはそれぞれの方向へ進化を遂げていく。海外の動向をなぞるのではなく、「日本的ハードロック」「J-ROCK」という独自ジャンルを築き上げつつあったのがこの時期だ。メタル、ヴィジュアル系、ポップロックが交錯し、まさに“多様化”の萌芽がここにも現れていた。
LOUDNESS – Loudness
アメリカ市場進出期を経て帰国した彼らが放った、セルフタイトルの通り“自らの存在意義”を再確認する一枚。華美な要素を抑え、リフ主体のストレートなメタルサウンドへと回帰しつつも、プレイには熟練のテクニックと国際的スケール感が宿る。「Slaughter House」「Black Widow」などの攻撃的ナンバーは、80年代的様式美を保ちつつも、90年代に通用するヘヴィネスを提示した。世界を見据えながらも、自分たちの核を見つめ直した過渡期の重要作である。
LUNA SEA – IMAGE
X(後のX JAPAN)以降のヴィジュアル系ブームの中で、圧倒的存在感を放ったセカンドアルバム。耽美でダークな世界観と叙情的メロディ、そしてポストニューウェーブ的な浮遊感を融合させ、ハードロックを新しい感性で再解釈した。SUGIZOとINORANのツインギターが描く幻想的な音像は、海外のトレンドとは一線を画し、まさに“日本の90年代ロック”の出発点となった。美と激情が共存する、時代の転換を告げる名盤。
B’z – RUN
日本のメインストリームにおいて、ハードロックの精神を最もポップに昇華させたのがB’zだった。『RUN』では、初期のデジタル色を抑え、アメリカンロック的な生音志向へとシフト。「ZERO」や「Out Of Control」に見られるグルーヴとスピード感は、当時の日本ポップスには異例のハードさ。商業的成功とバンドサウンドの融合を実現し、ハードロックを日本の大衆音楽へと根付かせた象徴的作品だ。
XからX-JAPANへの改名と海外挑戦
1991年の『Jealousy』で日本のメタルシーンの頂点に立ったXは、同名バンドとの混同を避けるため“X-JAPAN”へと改名し、世界進出を目指した。しかし、その挑戦は決して順風満帆ではなかった。言語の壁、そして文化的ギャップが立ちはだかる。さらに運命の皮肉だったのは、挑戦の時期がグランジの台頭と重なってしまったことだ。どれだけ完成度が高くとも、X-JAPANの華美でドラマティックな様式美は、当時の西洋ロック界では「古い」と受け取られてしまった。それでも彼らの挑戦は、後に続く多くのアーティストの道標となったという点で、決して無駄ではなかった。
最後に
こうして振り返ると、1992年という年は、ハードロック/ヘヴィメタルにとって“終わり”ではなく、“再定義”の年であったことがわかる。グランジの台頭によって、派手なルックスや技巧主義は時代遅れとされたが、その裏で多くのアーティストたちが新しい表現を模索し、ジャンルを越えて可能性を広げていた。1992年のHR/HMシーンは、決して一枚岩ではない。だが、その混沌こそが、新しい時代の始まりを告げていた。メタルは死ななかった。形を変え、場所を変え、聴く者の心に寄り添い続けた。1992年、それは「終焉」ではなく「変革」の年だった。
といった感じで、3回に分けてHR/HMにとって大きな転換期になった1980年、1986年、1992年を取り上げた(あと、番外編で1987年)。このあとのHR/HMはシーンの細分化もあって、特定の年を転換期として扱うのが難しい。あえて取り上げるとしたら、ニューメタルがシーンの中心になったり、メタルコアが出てきたり、日本でメロスピやメロデスが盛り上がった2000年前後だろうか。こちらについては、気が向いたらやりたい。


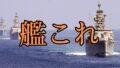

コメント